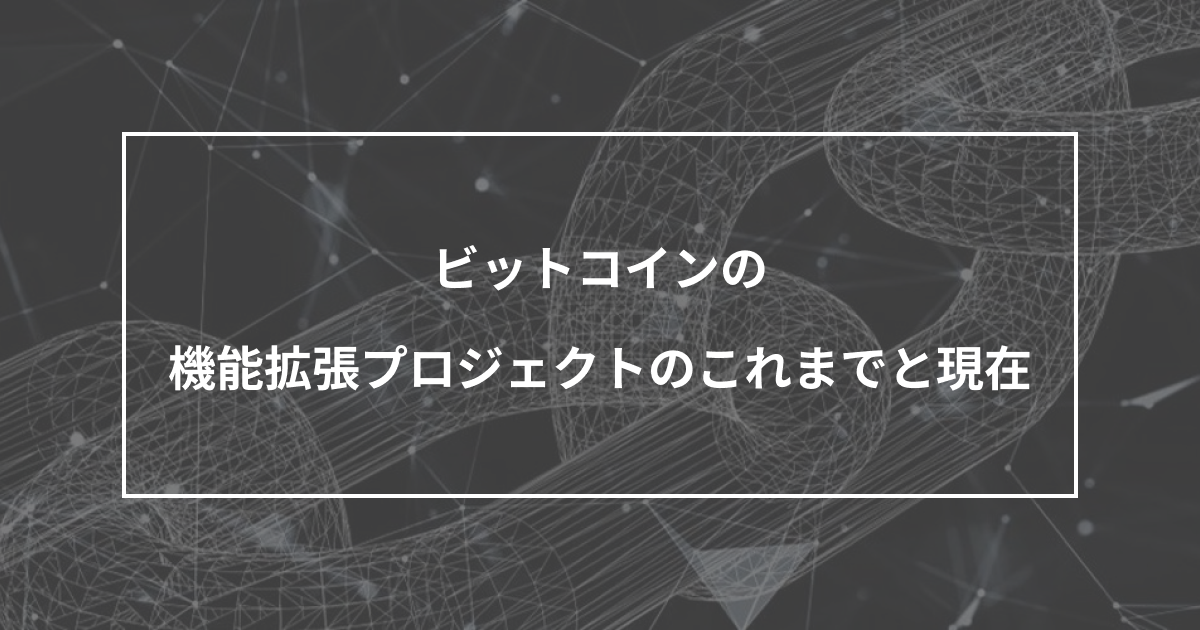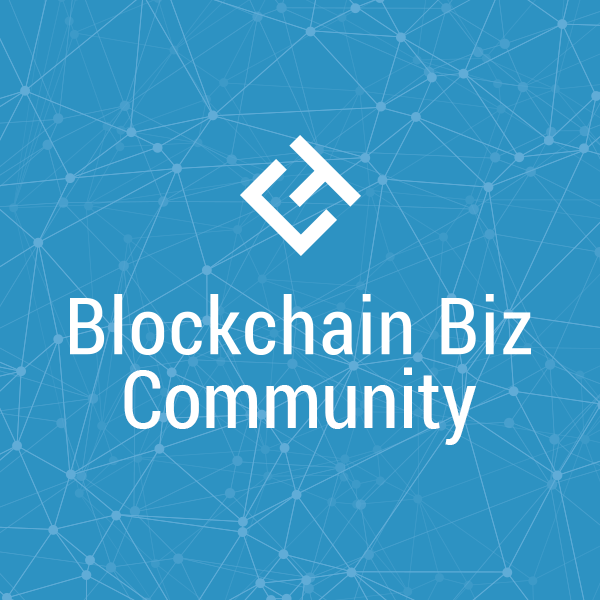ここのところICOという言葉を耳にする機会が増えてきました。ICOとはInitial Coin Offeringの略で、ブロックチェーン技術を用いた仮想通貨の発行を通じた、クラウドファンディングの新しい形のものです。2017年に入ってからは、ICOを通じて数億円規模の資金を調達している企業も出ており、その注目度は上がっています。今回は、このICOについて見ていきましょう。
目次
ICO(Initial Coin Offering)とは
Initial coin offering(ICO:新規仮想通貨公開)とは、そのサービスやアプリケーション内で利用できる仮想通貨を、まだサービスを開発の段階で先行発行することで、クラウドファンディングの形の資金調達を行うことを指します。企業の株式公開であるIPO(Initial Public Offering:新規株式公開)にちなんでICOと名付けられています。
サービス提供者側にとっては、サービスをリリースする前に通貨部分を先に売り出して資金調達をすることで、開発やサービス展開への費用をまかなうことができます。そして、ICOに応じてくれたユーザーに対しては、サービス開始後にお得な形でサービスを受けられるよう、定価より安い金額設定で通貨を販売します。
ICOは以前はクラウドセールと呼ばれていましたが、ここ最近ではICOという呼び方の方が一般的となってきました。クラウドセールについては、過去に記事を書いていますので、詳しくはそちらをご覧下さい。こちらの記事にもある通り、ICOを理解するために、kickstaterやCAMPFIREといったクラウドファンディングを思い浮かべると良いです。クラウドファンディングではリターンとして製品の購入権などが得られますが、ICOでは仮想通貨が得られる仕組みになっています。
クラウドセール - ブロックチェーンによるクラウドファンディングの新しい形
ICOは比較的新しい概念であるので、2017年7月現在で、日本におけるICOの法的位置付けは完全には定まっていません。しかし2017年6月8日の参議院財政金融委員会で言及されているように、資金決済法に基づく仮想通貨交換行に対するルールまたは金融商品取引法に対するルールが適用されると考えられ、今後は株式による資金調達であるIPOと同様に規制が導入される可能性があります。また、日本だけでなく、米証券取引等監視委員会(SEC)においても、調査が始まっています。
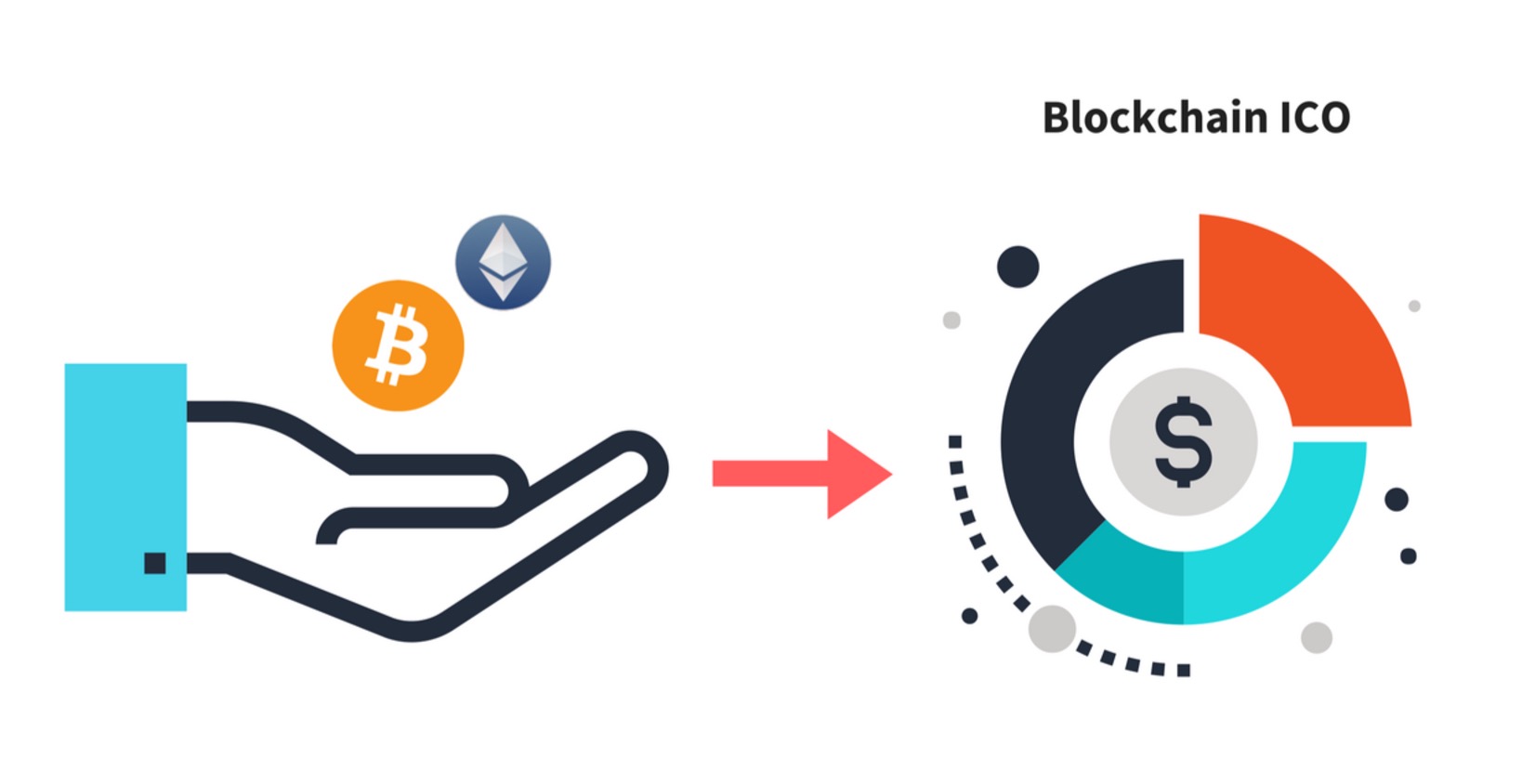 画像:Blockgeeks
画像:Blockgeeks
ICOという概念は、Ethereumが初期の頃ICOを通じて資金を調達したことから徐々に浸透していき、分散型UberのArcade Cityや、分散型未来予測市場であるAugurといったサービスも、ICOを通じて資金調達をしています。
このようにICOにおける仮想通貨は、IPOにおける株式と似ていますが、異なる点もあります。例えばビットコインは、ネットワークを維持するためのマイニングに対して報酬が与えられるので、基本的にはビットコインエコシステム維持のためにビットコインが発行されています。それと同様に、ICOをする企業・サービス自体の価値を考えるだけでなく、重要であるのはその仮想通貨の裏にあるブロックチェーンモデルの妥当性や使い続けるインセンティブも同時に考えなければいけない、という点です。
Initial Coin Offeringのメリット・デメリット
メリット
一つのメリットとして、ICOは基本的には一般人でもVC(Venture Capital)のように投資に参加できるという点です。未公開プロジェクトに対して投資するべきかどうか、その投資対象が今後成功するかどうかを見極めて、個人レベルで実際に資金を投じることができるのは利点であると言えるでしょう。
またブロックチェーンを利用したものであるので、どれだけ離れていても投資ができる、第三者機関が不要、といったブロックチェーンによる恩恵を受けることができます。Kickstarterなどのクラウドファンディングでも同様の利点がありますが、クラウドファンディング事業者という第三者機関が存在します。その点、ICOはトークン発行体と投資家という二者間のみのやり取りであるので、第三者機関が完全に不要となります。
デメリット
ICOのデメリットとして、ICOの対象となるプロジェクトや企業の信頼性を定量的に測定することが難しいという点が挙げられます。ブロックチェーン上に仮想通貨を発行して販売するという行為は誰もが可能なため、ICOをすることによってその事業を完遂させることができるかということに関して、十分な情報が入手できません。通常のIPOであれば財務諸表などを中心としたデューデリジェンスがなされますが、ICOの場合そのような行為は、通貨を購入しようとしている一般のユーザーにとっては難しいものとなってしまっています。
近年では投資の妥当性の判断材料となるホワイトペーパー以外にも、対象となるプロジェクトを正当に評価するためにGitHubを通じて開発コードを確認することによっても判断されます。しかしICOの場合、ブロックチェーンに関するコードの妥当性の判断は非常に難しいです。特にスマートコントラクトや分散アプリケーションといったコードは実際に正しく動作するかどうかも分からないことが多いため、その判断は困難を極めてしまい、事業に対して定性的な評価に留まってしまう可能性があります。
今後、どのように投資判断をしていくのかは大きな問題になるでしょう。
Initial Coin Offeringの事例
Brave
Mozilla前CEOのBrendan Eich氏が立ち上げたブラウザ開発企業Braveが、2017年6月になんとICOを利用して、30秒以内に3500万ドルを調達しました。BraveはICOをするために自社独自の通貨Basic Attention Token(BAT)を10億枚発行し、その総額は3500万ドルに相当する15万6250ETH(イーサリアムブロックチェーンに関連した仮想通貨)です。
現状のネット広告のシステムに問題があると考えているEich氏は、ブロックチェーン技術を使って広告システムを効率化し、広告主・出版社・ユーザー全ての関係者がメリットを享受できるような仕組みを提唱しています。
Braveは同社のブラウザのメリットとして、読み込み時間の短縮や強いプライバシー管理機能を挙げているほか、ユーザーはBraveのブラウザ上でコンテンツを読むだけでお金を稼ぐことができるようになるかもしれません。
しかし、本ICOには問題点も存在します。実際に独自通貨BATを購入した人はわずか130人しかおらず、中には一人で460万ドル分のBATを購入した人もいました。そして全体で見ると、投資総額の約半分がたった5人の投資家によりなされており、投資額上位20人が発行されたBATの3分の2を手にしたとCoindeskは報じています。
ICOは判断の難しい投資であるので、どの程度公募されるべきかという判断は難しいですが、個人投資家が入り込める余地を残しておくというのは、ICOが一般化するにつれて重要な課題になってくると考えられます。
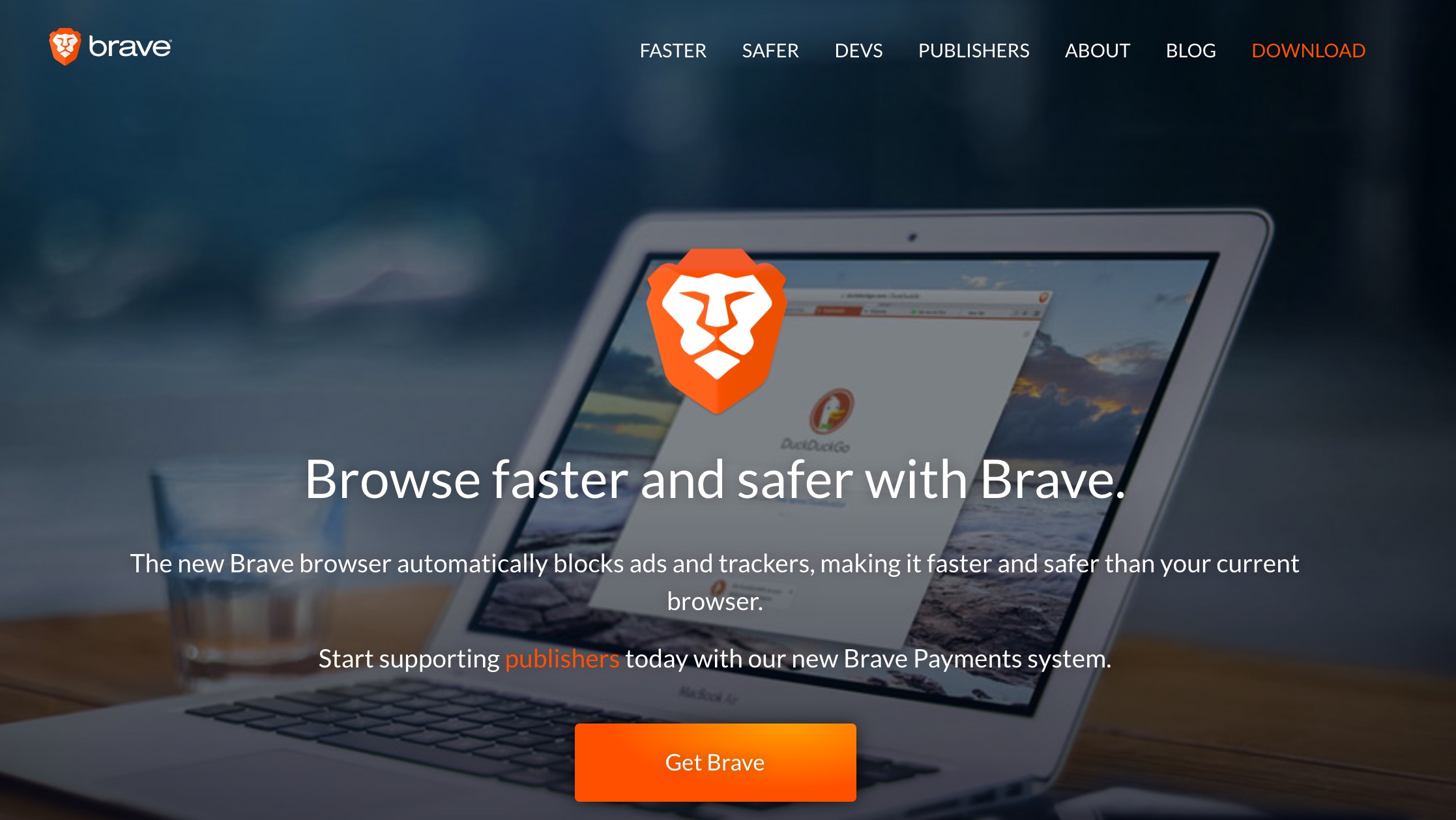 画像:Brave
画像:Brave
TenX
シンガポールでのブロックチェーンのスタートアップTenXが2017年6月下旬に、開催された通貨販売で8000万ドルに近い資金を調達しました。同社の記事によると、TenXは金額にして約8000万米ドルの価値となる24万5832ETHほどを調達しました。これらETHは同社独自のPAYトークンに交換されました。
TenXの提唱するプロトコルは、異なるブロックチェーン間での迅速かつ安全な取引を実現するものです。仮想通貨からデビットカードへ移し、店舗での決済も可能としています。約4000人が個人として通貨販売に直接参加しましたが、団体として資金をプールして通貨を購入した者もおり、ICOは7分も経たずに終了しました。以降は、PAYは仮想通貨市場でトレード可能となり、販売量が限定されていた最初の販売で通貨を購入できなかった4万人近くの参加者が、もう一度通貨購入の機会を得ることとなります。
 画像:TenX|Medium
画像:TenX|Medium
仮想通貨を利用した資金調達方法であるICOは、より資金調達をしやすい環境作りのための方法であると考えられます。将来的には、ICOというエコシステムががより身近になり個人レベルでも簡単にサービスへの投資ができるようになるかもしれません。しかし一方でICOを利用した詐欺行為も増えてきており、参加の際には十分な注意が必要であるので、これを機に理解を深めておくと良いでしょう。